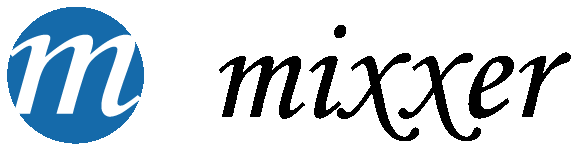日本では文字が使われるようになったのは5世紀以来だから弥生時代や古墳時代初期に関する書物はほとんどない。わかることは中国の史書に残されていた記述や発掘した出土品から示唆できること。漢書の地理志によると、倭国(当時の日本)には100当たり小国が存在していた。そして、その一国は中国の出先機関である楽浪郡に遣いを送った。先進国の中国を後ろ盾にしたがっていたことから、その倭国では権力闘争が起こっていたことを示唆できる。
後漢書の東夷伝にも倭国のことが記述されている。今回は洛陽にいる光武帝に遣いを送る王がいて、金印が与えられたと書かれている。この王の身分はわからないが、福岡の志賀島付近で「漢委奴国王」と刻印されている金印が発見された。その解釈に諸説あるが、中国で地域王権の一つと認められた人がいたと考えられる。
そして、西暦107年に160生口(奴隷)を中国に献上した王がいたと記述されていることから、また相当力持ちの王がいたと考えられる。
2世紀の後半で「倭国大乱」が起こったと記述されている。魏志の倭人伝に同じことが書かれている。恐らく、小国同士の間に権力衝突が頻発し、大乱を起こした。そして、小国の王が先進国である中国に遣いを送り、優れた書物を手に入れることによって、有利の立場に立つことを求めたと考えられる。この大乱の背景で30か国くらいが統一して、卑弥呼という新しい王を推戴したとされている。
このこれでどうして日本で統一統率が見えてくるかというと、弥生時代では稲作を始めたから。縄文時代までは農耕がほとんどなく、大体採集、漁労、狩猟で食料を手に入れた。今までと違って、稲作は共同作業。植え付け、育成、収穫を団結でしなければ作れない。そして、この集団を統率する存在が必要になってくる。古墳時代に近づくと武力で納める統率が見えてくるが、最初は武力より呪術(シャーマニズム)が認められた。その訳も稲作にある。植えるだけで稲は育たない。田植えから刈り取りまできちんと見計らう必要がある。科学知識が進んでいなかった時代だから、そのタイミングを決めるのが神事だった。
魏志の倭人伝によると卑弥呼は遣いを送って「親魏倭王」と呼ばれるようになった。そして、明帝に金印紫綬と銅鏡100枚を授けられたと書かれている。金印紫綬というのは中国で授けられていた刻印の中で最上級の金印。紫綬というのは紫色の綬のことです。天皇が使っている刻印の次に朱綬があります。朱綬のついた刻印は側近の人にしか授けられていなかった。紫綬はその2つを除いて最上級で、大切な大臣に授けられた刻印だった。そして、銅鏡は当時の人にしては魔力の存在だった。科学知識が進んでいない時代の人々からすると、自分の姿を映す鏡は非常に不思議だったと考えられる。100枚が授けられた卑弥呼は魔力を授けられたとみられたと考えられる。
卑弥呼の死後、男王を立てようとしたと書かれているが、邪馬台国は混乱に陥った。最終的に卑弥呼の宗女である壱与を女王にすれば取り戻すことができたと書かれている。この記述から当時の倭国を治めるのは宗教的な力を持つ者のみだったことが示唆できる。古墳の副葬品でもわかることができる。3世紀後半から7世紀は古墳時代。そして、4世紀前期ぐらいまでは古墳に遺体と一緒に埋葬された副葬品は勾玉、銅鏡などの宗教的なものが多かった。だけど、それ以来、古墳が巨大化しつつ、宗教的なものの代わりに武具、馬具などの軍事的な副葬品が見られる。
理由はまた稲作にあると考えられる。農業をやっていくうちに天候などによって農作もあれば凶作もあることが分かってきて、宗教的権威者が弱まってしまう。そのすきに武力を持つ人は隣接する国々を次々と侵略していくと考えられる。だけど、詳細はわからない。書物は残されていない4世紀のことは「空白と4世紀」と呼ばれている。
なぜ空白かというと、4世紀に入ると中国の北方から匈奴が南下してきて、五胡十六国時代が始まり、倭国と疎遠してしまう。同時、韓国では武力の背景に統一国家が生まれてくる。高句麗は楽浪郡を滅ぼし支配する。韓国の三韓はそれぞれ、百済、新羅、伽耶に変化していく。百済と新羅は統一国家だけど、伽耶は小国連合だった。こんな不穏の中、倭国と触れ合うことがほとんどなく、史書から消える。
5世紀に入ると中国の史書に倭国のことは再び出てくる。5世紀では畿内の地方でヤマト政権があることから、当時までの4世紀の日本では韓国と同じく統一していく過程が武力の背景で行われていたと示唆できる。どうして武力で統一していたことがわかるかというと、宋書で倭の五王について述べている。その中の一人は「武」と記述され、雄略天皇だと考えられている人が軍事活動を補うために朝鮮半島南部の鉄資源を手に入れたくて中国に政権を得ようとする。鉄資源を求めることから、戦に取り組んでいたことが考えられる。この過程で5世紀が続きヤマト政権が広がり、飛鳥時代になっていく。